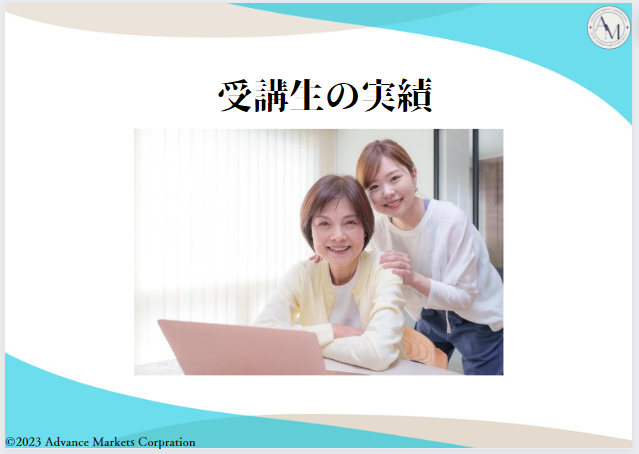こちらにお越しいただきありがとうございます。
この記事では、初心者向けに、読みやすい記事を書くコツをお伝えしております。
ブログ初心者向けの記事が読みやすくする[文法編]
①主語と述語を近づける
先ず、主語と述語を近づけて、シンプルな文にしましょう。
自分で後から読み直して、なぜか理解しにくいかも、と感じたら、間の修飾語をカットしてみるなど、文をシンプルにしましょう。
主語「誰が」、述語「どうした」を近づけてみてください。
例えば、「私は我が子に施した家庭教育の実体験を元にしたブログに集客するためのSEO対策が得意です」
上記の文章、ちょっと意味が分かり辛くないですか。
主語「私は」と、述語、「得意です」が遠すぎるからですね。主語と述語の間に色々な言葉が入ってるから、シンプルに伝わりにくくなっています。
では、「私はブログに集客するためのSEO対策が得意です。そして、我が子に施した家庭教育の実体験を元にブログを作りました。」
これなら、きっと分かりやすいと思います。
②一つの文章には1主語と1述語にする
主語と述語を近づけたら、今度は、1つの文章には、主語は1つで、述語も1つにしましょう。
接続詞でつなぎ、主語と述語が複数あると、誰かどうした?がごちゃごちゃになり、意味が伝わりにくい文章になってしまいます。
主語と述語は1つで、いったん「。」とし、文章を終わらせることを意識しましょう。
③無くても意味が通じる接続詞は削る
なるべくシンプルな文章で、読み手にストレートに伝えたいものです。
例えば、「そして、だから」や、「また、および」、「しかし、でも」などです。
文章を書いていると、接続詞は良く登場しますが、接続詞の使いすぎには注意しましょう。口語では、接続詞が多くてもいいのですが、文字にすると若干、冗長に感じてしまいます。
二重の意味になっている接続詞は、あとで読み直して削ることをおすすめしてますが、全ての接続詞を削りましょうと言ってるわけではありません。
読者の目線に立って、適切な位置に適切な接続詞を入れて、わかりやすく表現しましょう。
ブログ初心者向けの記事が読みやすくする[表現編]
①代名詞をなるべく使わない
代名詞とは、こそあど言葉ですね。「これ、それ、どれ、あれ」のような言葉です。
口語なら代名詞を使う方が、すっきりして良いのですが、ブログのような記事では、なるべく使わない方が、意味が通じます。
あなたが指す「これ」が、読者にちゃんと伝わっているでしょうか。読者が他のことを「これ」と思いながら、読み進めていると、意味がわかりにくい文章となり、離脱してしまう可能性もあります。
読者が迷子にならないように、めんどくさくても、「これ」が指す言葉をしっかりと入れていきましょ。
国語の読解問題を思いだしていただきたいのですが、問題でよく「それ」が指すものが何か答えないという問い、ありましたよね。
問題になるほど、人は「それ」が指すものを正しく答えらえないことも十分考えらえます。
ですので、それは何かしっかり表現することが大切です。
それが指すものは前文をしっかり理解してないと、分かり難いですし、文章全体をさらりと読む人もいらっしゃいます。
途中から読んでも、意味が分かるように、親切、丁寧な表現を意識しましょう。
②斜め読みされても、理解できる文章
とにかく、読者は忙しくて、自分が気になるところだけを斜め読みしていくと思っておいた方が良いです。
そこで、途中からでも、斜め読みされても、理解しやすい文章だと、興味を持って、もう少し先まで読み進めてくれます。
あなたも何かを検索したときのことを思い出してみてください。記事の文字を一字一句しっかりと読むことはあまりないと思います。
私もそうですが、無意識のうちに結構、斜め読みして、読み飛ばすことも多いと思います。
私達、記事を書く側にとっては、上から下まで一字一句読んでいただけるように書いていますが、残念ながら、読者はそうではない可能性があります。
そこで、読み飛ばされても、理解できるようにするテクニックをご紹介します。
- 箇条書き
- 文字の太字や色付け、装飾効果
- 画像や図で分かりやすく
- 吹き出しで目立たせる
要所要所に、目立たせるための工夫があれば、文章を読んでなくても、書いてあることが読者に理解してもらえます。
だらだらと文章を書いてるのを読むより、箇条書きの方が、分かりやすいと思いますよね。
さらに、文章で書いていることを図によって表現されていると、見てすぐに理解できますよね。
文字が赤字や太字や下線があれば、目立つのでそこは読者の目にとまりやすいですよね。
そのような工夫をして、読者に理解していただけるように工夫することで、質の良い記事となります。
③同じ文末表現は、繰り返さない
例えば、「~です。」「~です。」というような同じ文末表現を繰り返すと、幼稚な印象を与えてしまいます。
韻を踏んでいるようなリズムで、気持ち良く読めそうな気がしますが、楽曲ではないので、同じ文末表現を繰り返すと、文章全体のリズムは悪くなります。
どうしても、同じ文末表現を使いたくても、別の表現に言い換えるようにしましょう。
④断定表現にする
文章を書く時に意識して欲しいのですが、あいまいな表現、例えば「~だそうです」、「~らしいです。」です。
あいまいな表現を多用していると、この記事の内容を信じても大丈夫だろうかと、読者を不安にさせてしまいかねないのです。
でも、自分が調べた情報が間違っていたらどうしようと不安になる気持ちは本当に良く分かります。
間違った情報を提供しないように、しっかりとリサーチした上で、記事を書くようにしましょう。
読者に役立つ記事を書く事が私達の役目ですので、事前に知識や下調べはしっかりと行うようにしましょう。
⑤同じ意味の言葉を重ねない
同じ意味の言葉を重複して使わないようにしましょう。
例えば、絶対に必須!、必ず必要!、約500円くらい、など。
普段、何気ない会話で、同じ意味の言葉を重ねても、何も違和感はないのですが、文章にするとちょっと違和感がでます。
文章を書いたあとに、読み直して、二重表現が無いかチェックしてみましょう。
ブログ初心者向けの記事が読みやすくする[見た目編]
①1文は約50文字
文章はある程度短く区切り、理解しやすい意味にまとめるようにしましょう。また、約50文字のまとまりにしておくと、一定のリズムがあり、読みやすくもなります。
無理やり、50文字にする必要はありませんが、極端に長かったり、極端に短い文章は避けた方が良いでしょう。
文章が長すぎてしまう場合は、1文を分割して、短く端的な表現にしましょう。
一つの文章で、伝えたいことは一つだけを意識すると、シンプルで理解しやすい文章になります。
文章が長すぎると、主語と述語と修飾語など多く入り、読者が意味を理解しにくくなりますので、とにかく1文は50文字を意識しましょう。
②約150文字で改行する
1つの文章のかたまり、ブロックは約150文字にしましょう。
この方法は書籍などの紙の媒体と大きく異なり、WEBライティング特有の書き方です。
最近では8割の人がスマホで検索しますよね。そして、スマホ画面いっぱい文字が書いてある記事を見て、あなたは読みたくなるでしょうか。
私なら、さっと別のサイトに行ってしまいます。
このように文字が詰まっている記事では、読者は読む気をなくしてしまいます。
ブログの記事は、あるまとまり、つまりブロックで改行しましょう。おすすめは、3文くらい書いたら、改行すると良いと思います。
そして、ひと呼吸おく感じで、意味もブロックでまとめるように意識すると、なお読みやすい記事になります。
なぜ、150文字かというと、一般的に人がひと呼吸で読みきれる文の量が、150文字だと言われています。
そのため、150文字で改行をして、文章と文章の間に空白の行を作り、ひと呼吸おいてもらうようにしましょう。
最近では、1行で改行するスタイルも出てきましたね。文と文の間、行間を開けると、ぐっと文章が読みやすくなります。その効果を期待して、1文で改行しています。
でも空白が多い分、せっせとスクロールしないといけないので、私は指が疲れてしまいそうで、あまりおすすめしておりません。
ブログ初心者向けの記事が読みやすくする[話題編]
①結論ファースト
結論ファーストとは、結論を最初に書くことです。特にブログ記事では、結論を一番に伝えることが何よりも重要です。
先に結論を書いてしまうと最後まで読んでもらえずに、離脱されるのが心配という方もいらっしゃると思いますが、結論を先延ばしにしている記事を読む気になりますかね。
現代社会の方は忙しい隙間時間で検索をしていることを想像してみてください。忙しい中で、結論がなかなか書かれてない記事を結論が出るまで読むとは思えないです。
結論がはっきり書かれているような記事の方が、読み進めくれると私は思います。
結論がなかなか書かれてない記事こそ読んでもらえない可能性が高いと考えて、結論ファーストな書き方を意識して欲しいと思います。
部下が上司に仕事の状況を説明するなど、ビジネスで使われるPREP法をご存知でしょうか。
PREP法は、結論 → 理由 → 具体例 → 結論 という順番で相手に理解してもらうフレームワークです。
私もビジネスマン時代が長いので、上司に報告するときは、このPREP法を使います。
この方法を使うと相手に伝わりやすく、余計な思考が不要で、すっきりします。
WEBライティングは、最後に落ちなどは不要ですので、先ずは読者の知りたい答えを伝える、それを意識して記事を書きましょう。
②話題を散らさない
記事の本題以外の話に、話題が反れそうになった場合は、短く潔く終わらせましょう。
本題以外を書いてはいけないと言ってるわけではありませんが、話題が散らかると読者が知りたい情報ではないと感じて離脱してしまう可能性もあります。
本題にしぼり、本題に対する答えは、長く丁寧に書きましょう。
しかし、丁寧に書き過ぎて情報過多になり、返って読者を混乱させたり、分かりづらい記事にならないように意識しましょう。
具体的には、前置きは短く、補足情報は簡潔に書くようにしましょう。
私達は読者にとって有益な情報を提供します。情報を厳選し、重要な点は長く丁寧書きましょう。
どうしても、補足情報も書き足したい場合は、別記事にして、〇〇については、こちらをご覧ください、と内部リンクを活用すると良いでしょう。